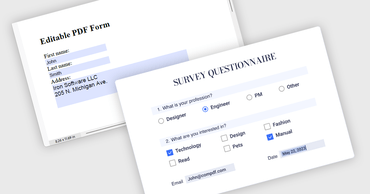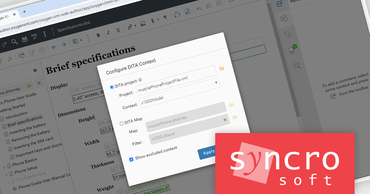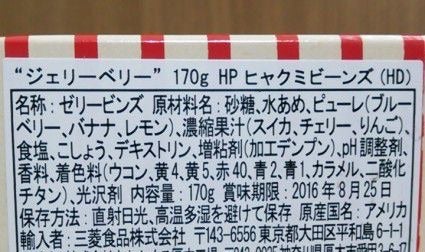石原慎太郎東京都知事の尖閣諸島購入の動きに端を発した日中関係の悪化は、日本の経済人、政治家、役人の予想をはるかに上回る段階にまで進んだ。常日頃は多くの人が顔をしかめる「日中一触即発」「日中衝突」といった、夕刊紙の根拠のない扇情的見出しが、今回ばかりはリアリティを持つほどの事態に到っている。言うまでもなく、ここまで日中関係が悪化した原因は双方にあるが、日本側で指摘すべきは「中国側の反応、対応を完全に読み間違えた」ことにある。日本サイドには中国は「(日本の実効支配という)尖閣の現状を受け入れており、日本側が従来より一歩くらい前に出ても、表面的な批判と多少のデモ程度で終わるだろう」という希望的観測があった。日本側では民主党が支持率回復のために石原都知事の尖閣に関する動きを利用しようという邪心もあっただろう。
「高成長の終わり」と「残された格差」
日本の政官界はある意味で、中国の「反日」には慣れっこになっており、尖閣国有化の動きに対する中国の初動段階での激烈な反応を的確に解釈できず、対応も鈍かった。早い段階で日中の指導者がホットラインを通じて意思疎通し、双方で過剰な言辞や行動を取らず、終息させるという合意ができれば事態はここまで悪化しなかっただろう。状況を一言で言えば、破壊的段階にある。「日中国交回復以来で最悪の状況」という表現はしばしば使われるが、「最悪」といっても双方が努力すれば旧に復することもあり、救いはある。だが、「破壊」が起きれば元には戻らない部分も出てくる。とりわけ、経済関係は投資と人材育成という、壊れたら捨てるしかないものを抱えているだけに、状況は多くの人が考えるよりもはるかに厳しい。
「経済関係にとって厳しい」というもう1つの理由がある。中国経済の悪化である。悪化といっても、ギリシャやスペイン、イタリアなどユーロ圏の経済危機に伴う輸出の減少といった一過性のものや循環的な景気悪化ではない。1978年に鄧小平氏が発動した「改革開放」政策による30年超の高成長の構造的な変化、端的に言えば、「高成長の終わり」という時代の転換を指している。
中国の指導者もテクノクラートはもちろんビジネスマンや庶民すら認めないが、中国は着実に低成長期に向かいつつある。昨日は大空港が完成し、今日は超高層ビルが開業し、明日は新幹線が走り出す、といったインフラ建設の嵐や、収入が右肩上がりに増加し、マイカー、ゴルフ、海外旅行など今までにない経験を毎月、毎年味わうといった、熱狂の経済成長は終わりに近づいている。残るのは、沿海部と内陸の発展格差、中流層と労働者・農民の収入格差、高度成長期を謳歌した既得権益者と遅れてきた「80后(80年代以降生まれ)」「90后(90年代以降生まれ)」たちとの人生のチャンスの格差だ。
社会に漂う不安と焦燥感
中国社会の中には様々な格差に対する不満とともに、格差を埋めるシナリオが高成長の終わりによって消えてしまうのではないかという不安が漂っている。今回、尖閣国有化をめぐって北京、上海、広州といった大都市だけでなく、100以上もの地方都市で激しい反日デモや破壊行為が起きた理由は社会に漂う時代の転換期の不安、焦燥感に裏打ちされているといってよい。その象徴がすでに多くの中国ウオッチャーが指摘している「毛沢東の肖像写真」である。
デモや破壊の際に毛沢東を前面に押し出すのは、胡錦濤政権への明確な批判であり、次に来る習近平政権への期待感の薄さを示す狙いだ。また、日本企業への焼き討ち、収奪、放火、破壊で掲げられた「愛国無罪」の主張は、毛沢東の発動した文化大革命(1966年-76年)で紅衛兵(毛主席を支持する過激な学生や若い労働者たち)が掲げた「造反有理」のスローガンそのものだ。
文化大革命は毛沢東による改革派に対する権力闘争だったが、今回は一部でささやかれている薄熙来・前重慶市書記を支持する一派による権力闘争の色合いは薄い。むしろ共産党一党支配体制への嫌悪感、経済状況の悪化に対する不満、時代の転換点における焦燥感が大衆を突き動かしている。
中国の指導部は今回、そうした大衆のエネルギーを日本に対する交渉カードにし、胡錦濤政権の最後に何かの外交的成果をあげ、花道にしようとした節がある。それは2005年などの反日とは異なる政治的な動きだ。だが、9月18日の柳条湖事件の記念日以降、中国政府はデモや破壊行為の鎮圧に転じた。「愛国無罪」を掲げて政府機関への攻撃が起きる危険を察知したからだ。あのまま反日の大衆運動を放置すれば、反右派闘争や文化大革命のような運動に大化けする可能性を感じたに違いない。
生産拠点は東南アジア、南アジアへ
では、日本企業はこうした状況にどう対応すればよいのか。重要なのは、中国が生産拠点としては、ある段階の役目を終えたという認識だ。中国は過去10年間の異常な急成長の結果、人民元は上昇、人件費も高騰し、モノを生産するには不利な場所になってしまった。中国で生産し、世界に輸出するという輸出基地的なビジネスモデルが通用しなくなったのは当然として、中国国内市場で販売するモノをつくるにしても、多くの商品分野で高コストによって不利となっている。むしろ、東南アジアや南アジア、場合によっては日本国内でつくった方が競争力があるものすらある。そうした生産拠点としての中国見直しは不可避といってよい。
生産拠点としてみた場合、縫製、靴、雑貨、家電など労働集約的な製品はベトナム、ミャンマー、カンボジアなど後発のASEAN(東南アジア諸国連合)諸国やインド、バングラデシュ、スリランカなど南アジア諸国、IT関連や自動車関連などやや高度な製品群はタイ、インドネシア、フィリピンなど先行ASEAN諸国で生産した方がコスト的に優位だ。中国国内市場向けの商品でもASEAN諸国で生産すれば、ASEANと中国が結び、2010年1月に発効したACFTA(中国ASEAN自由貿易協定)で、多くの商品は無税ないしは低関税で中国に輸入できる。中国国内で生産しなくても、中国市場でモノは売れるのである。
「反日デモ」はまた必ず起きる
日本企業にとって今回、大きな衝撃だったのは工場や生産ラインが破壊された企業が出たことだ。設備は損害保険でカバーされるにしても、工場が復旧するまで生産が停止することで顧客に対する責任を果たせなくなり、企業の信用問題に関わってくる。企業としては工場の移転を検討せざるを得ない状況だ。従来のように、反日デモが過ぎ去るのを首をすくめて待っていても、次の反日デモ、日本企業への攻撃は何かのきっかけで必ず起きる。生産停止、供給停止のリスクを回避しようとすれば、日本企業は中国以外の場所にも生産拠点を置く「チャイナ・プラス・ワン」戦略か、中国工場を別の国に移転する戦略を取らざるを得ない。日本企業にとって生産拠点としての中国の意味合いは大きく変質したのである。
日本企業の中国からの撤退は実は水面下ではすでに進んでいた。あまりのコスト上昇で、ベトナム拠点の拡充を急ぐ企業が多いのだ。多くの日本企業は今後も表だって中国から撤退するとは言わないまま、静かにかつ段階的に中国から生産品目をASEANなどに移し、工場のカギを締める段階になって初めて発表するといった動きを取るだろう。それでも多くの日本企業は中国に生産拠点を残す。巨額の投資をした工場を捨てるのは資金的にも難しいからだ。なんとか工夫して中国生産を続けながらも、中国から逃げ出す時期を見定めている。そんな日本企業が増えていくのは間違いない。尖閣をめぐって日中両国は大きく離反したが、ビジネスの面でも日中は家庭内離婚のような冷めた関係に移っていくだろう。